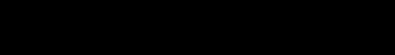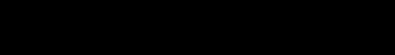|
駒澤大学野球部では、2年のときにレギュラーの座を獲得している。
1987年の東都六大学春季リーグの直前になって4年のレギュラーが骨折したため急遽出場した試合で、望は神宮球場のバックスクリーンにぶち当てたのである。
公式戦での初ヒットだった。
その後も憑かれたように打ちつづけて、駒澤大学の優勝に貢献している。
結局春季リーグが終わってみると、33打数19安打10打点、打率5割7分6厘で堂々の首位打者。二塁手でベストナインに選ばれたのだった。
翌1988年の春季リーグでも同じくベストナインに選ばれている。
5割7分6厘についてかれは言う。
「野村謙二郎さんのおかげです。かれは出塁するととにかく盗塁を敢行した。そしてほとんどセーフだった。ノーアウト二塁の場面で次打者のわたしは楽なものです。セーフティーバントを適当に転がしておけば三塁はかならずセーフですから、あとは私が一塁でセーフになれば1打数1安打、アウトになっても送りバントということで0打数0安打です。野村謙二郎のうしろを打てば、だれでも打率は稼げますよ。」
野村謙二郎・鈴木望の1、2番コンビは相当鬱陶しかったことだろう。
神宮球場での初ホームランについても聞いてみた。これは思い出深いにちがいない。
「あれは風ですよ。カゼ。追い風だったんです。いい風がふいていたものです。」
望の素顔は「朴訥(ぼくとつ)な好青年」とでも評すべきだが、意外にも大学時代、かれは「叱られ役」だったという。
「叱られ役というよりも、殴られ役といった方が当たっています。太田監督は野球よりもむしろ私生活に厳しい方で、しかも寮のすぐ前に住んでおられたので、門限破りなどが見つかると次の日は散々でした。」
太田監督と望の父章介は友人だった。
章介は、読売巨人軍のトレーニングコーチ時代「妥協のない鬼」と評された。
当時章介にシゴかれた選手が笑って言う。
「夢のなかで鈴木コーチに追い回されたことがある。こんな、夢のなかまで追っかけて来られたんじゃたまらん、と思った。」
類は友を呼ぶ。
二人の「鬼」が何やら相談したのかどうかわからないが、望は徹頭徹尾怒られつづけた。
「山下監督と太田監督のどちらが怖かったか?」
「うーん、最初に山下監督を見たときは、世の中にはこんなにおそろしい人がいたのだ、とびっくりしました。衝撃度では山下監督、パンチ力では太田監督です。」
大学時代も過ぎ去ろうとしていた。
それまでかれは「プロの世界」など思い描いたことすらなかった。
1989年のプロ野球ドラフト会議で東京読売巨人軍から5位で指名されたその当日も、かれは友人と連れ立って飲み歩いていたという。そのため自分が指名されたことも知らず、次の日になって野球部の仲間から聞かされた時も、どうせ冗談だろうと相手にしなかった。
こうして「東京読売巨人軍 鈴木望」が誕生した。

巨人軍練習場は読売ランドからすこし下ったあたりの小高い山の上にある。
望のプロ野球人生がここに始まった。
入団の翌年には、年明け早々の1月15日からさっそく新人だけのミニキャンプが行われる。同期のドラフト入団は大森剛(慶応大)、川辺忠義(川崎製鉄千葉)、吉岡雄二(帝京高)、佐久間浩一(東海大)、浅野智治(岡山南高)。
2月に入るとキャンプインだが、かれは二軍でスタートを切った。
さすがにプロの世界は厳しかったとみえて、1年目は二軍で36試合に出場しただけで終わった。
だが望は確かな手ごたえを感じ取っていた。
2年目には同じく二軍とはいえ、60試合に出場し179打数56安打、打率3割1分3厘の好成績を残している。
このころ、かれには気になることがあった。一軍と二軍のあいだで選手の入れ替えがまったくといっていいほどなかったのだ。
「巨人軍の中にチームが二つあるような感じでした。」
それもそのはずで、当時の一軍の内野陣は篠塚利夫、岡崎郁、原辰徳、川相昌弘、上田和明。そう簡単に入れ替えなどあろうはずもなかったのである。
練習後、同僚の前田隆とふたりで飲み歩く日が増えた。
いつになったら一軍から声が掛かるのか、見当もつかない。出口の見えないトンネル。いや、もしかすると出口はないのかもしれない。絶望的にながい二軍生活だったにちがいない。思えば、ここまで順風満帆な野球人生をおくってきたかれにとって、初めて味わう挫折感だった。
「いつかきっと俺たちの時代がやってくる。」
ふたりは虎視眈々とチャンスを待ちつづけた。だが結果的に、かれはついにこの壁を乗り越えることができなかった。
「何度かチャンスはあったと思います。ただ、野球そのものが云々ではなく、二軍の生活に妙に満足してしまった。プロで成績を残せなかった原因はそのあたりにあるのかも知れません。」
その後も二軍の試合に出場こそするものの「ほどほど」の成績ばかりで、自身の2年目の数字すら超えることはなかった。
こうして6年目をむかえた。
このころになって、一軍の不動の内野陣にも衰えが見え出してきていた。
1994年のシーズン終了後、篠塚利夫が引退。前年には上田和明が去っていた。また岡崎郁もその2年後には引退することになる。
「やっとチャンスが巡ってきた。」
5年目のオフに望は心中期するものがあったにちがいない。
わたしは少し前に「挫折」と書いた。
しかし考えてみれば、名手篠塚でさえ一軍に定着したのは入団4年目。岡崎郁も丸5年の歳月を要した。わずか数年の二軍生活などは当たり前で、挫折でもなんでもなかったのだ。
6年目のキャンプでも望は黙々とメニューをこなしていった。かれのプロ野球人生もようやく花開くときが来たかに思えたその矢先のことだった。とんでもない運命がかれを待ち受けていたのだ。それは「残酷」ともいうべき出来事だった。
「右ひざ半月板損傷」である。
(つづく)
|